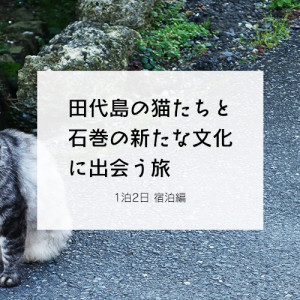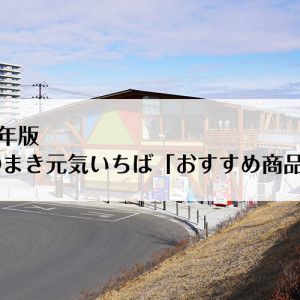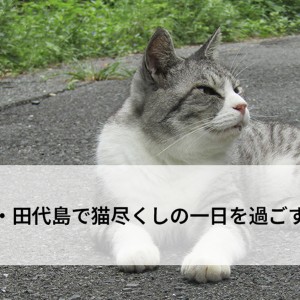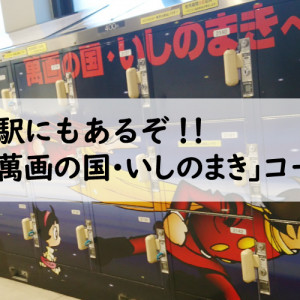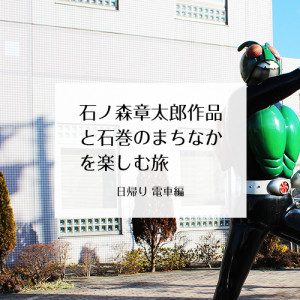《丸山正雄さん×片渕須直監督インタビュー》漫画家やアニメーターが生まれ、育つ街へ—マンガ文化を中心とした持続的なまちづくりのあり方を考える
2024年9月1日(日)、石巻市の「かわまち交流センター」にてアニメーション映画である『この世界の片隅に』の制作監督を務めた片渕須直さん(以下:片渕監督)と、『時をかける少女』などのアニメーション映画をプロデュースした丸山正雄さん(以下:丸山さん)によるトークイベントが開催されました。
イベントでは、同年8月31日と9月1日に「石巻名画座」の主催で上映された『この世界の片隅に』の制作秘話などに関する話がなされ、多くの来場者の関心を集めました。
トークイベント終了後に「石ノ森萬画館」の運営や石巻市中心街のまちづくり事業を行う「株式会社街づくりまんぼう」のメンバーが、丸山さんと片渕監督のお二人に「マンガ文化を生かしたまちづくり」をテーマにインタビューを行いました。
石巻市は『仮面ライダー』などの名作を生み出した石ノ森章太郎先生(以下:石ノ森先生)のゆかりの地。2001年には石ノ森萬画館が開館し、石ノ森先生が制作した作品の原画などが展示されています。石ノ森先生は1998年に逝去されましたが、その作品は多くの人々に愛され続けており、現代でも『仮面ライダー』シリーズでは新しい作品が生み出されています。
市街地では、漫画・イラスト・アニメーションなどを描きたい若者の創作活動を支援する「いしのまき MANGA lab. ヒトコマ」が開設されているほか、石ノ森先生の作品に登場するキャラクターのモニュメントが多数設置されている「石巻マンガロード」などマンガ文化を中心としたまちづくりが進められています。

マンガ文化を中心としたまちづくりを20年以上進めている石巻市。今後もマンガを活かしたまちづくりを持続的に進めていくための方法やあり方として、どのような内容が考えられるのでしょうか。そのヒントを丸山さんと片渕監督に伺いました。
新しいまちづくりの姿は人材育成 – クリエイターを育てることの本質とは
アニメーション業界で活躍する丸山さんと片渕監督は、石巻市が進めている「マンガ文化を活かしたまちづくり」をどのような視点で捉え、どのように考えているのでしょうか。また、今後もまちづくりを進めていくにあたって関わっていただけることがあるとすれば、どのような内容になるのでしょうか。お二人は、石ノ森先生の作品を活用するという視点とは異なる観点からお話を展開されていきます。
丸山:漫画家やアニメーター(以下:クリエイター)は収入が少ない職業でもあります。 イラストを描くなどの特技を持った人がやっていくのであれば、みんなでその挑戦を応援しつつ協力をした方がいいと思っています。
前提として、まちづくりとクリエイターを育成することは別だと考えています。ただ、漫画をテーマにまちづくりを進めていくとまちへ訪れる人は増えていくはずです。そのような現状なので、何をやるのか明確になれば、さまざまな関わり方ができると思います。
片渕:アニメーターの基礎である「動きに対しての感性」を高めることにつながることであれば、さまざまな活動ができると思っています。ピアノを幼稚園のころから習うように、カメラもその時期から習う方がいいのではないかと考える人がいます。ピアニストや音楽家になる人は、技術と感性が一体化していることを理解しています。感性と技術を一体化させるために、音楽を幼稚園や小学校の頃から習うんですよね。
最近は実写のカメラマン教育でも感性を磨くことに注力しています。アニメーションの動きや映画のカメラも音楽と同じで、感性を高めることを早いうちから行なった方がいいと思っています。 全員がプロのピアニストやアニメーターになることはないと思いますが、 基礎的な素養として感性を持つ人が増えるべきだと思うんです。
まちづくりを進めていくにあたって将来クリエイターになりたい若者の挑戦を応援しつつ、人材育成を行うことを提案された丸山さんと片渕監督。お二人は、続けてそのようなまちづくりを進める際に中軸にすべき考えや方向性をお話されました。
丸山:技術よりも心が重要であるということや、どのようにチームを組んだりもの作りを進めていくのかという考え方の問題に注目した方がいいと思います。現在まちづくりとして考えていることは、どんどん進めてほしいです。そこに、私たちが関わるとどんなことができそうか具体的に教えていただければありがたいです。 また、その土地に根付くためのまちづくりをするためにも何を継続するのか、どのような気持ちでどのような活動するのかを考えることが重要だと思っています。
片渕: 人材育成と産業を結びつけないことが大事だと思いますね。 基礎的な素養としてアニメーションの動きや漫画を作り出せる人を増やし、その人たちが作ったものがきちんと発表できる環境を整えるのが理想的かと思います。現在ではWEB上に掲載することも簡単にできると思いますし、その上で評価を得ていくのがいいと思います。

いいねと背中を押し、仲間同士で切磋琢磨できる環境を作る
冒頭では石巻市でマンガ文化を中心としたまちづくりにおいて取り組みたいことを明確化していく一方、将来クリエイターになりたい若者の挑戦を後押ししつつ、人材育成していくことに注力した方が良いのではないかというお話を伺いました。
石巻市の中心市街地には、漫画・イラスト・アニメーションなどの創作活動を行いたい子供たちや若者の活動拠点として「いしのまき MANGA lab. 」が開設されています。同施設では創作スペースがあるだけではなく画材の販売を行うほか、ワークショップなどさまざまなイベントも開催されています。いしのまき MANGA lab. ヒトコマを運営するスタッフが、未来のクリエイターに対して後押しできることはあるのでしょうか。丸山さんと片渕監督は次のように話します。


丸山:制作した作品やその過程を評価できる人がいないと、本人が本気になって取り組んでいても途中で挫折してしまうこともあると思います。 私としては仮に絵を描くのが下手だったとしても、他者が作品を評価しながら絵を描く能力を伸ばしていったり、絵の魅力を「いいね」と言ってあげることが必要だと感じています。
片渕:漫画家になる人他者との比較で悩むことがあります。例えば「あの人が考えたストーリーの方が面白い」「あの人の描く絵はすごい」と思うことですね。 ただ、クリエイターとしてはさまざまな悩みがありながらも一生懸命作品を作っているじゃないですか。その過程で他者の作品が優れていると思えるようになることは、同時に作品に対する魅力を理解できていることにもつながります。
クリエイター同士で競い合いをしたとき、どちらの作品が優れているのか理解できるようになれば感性を磨くことにもつながるんです。自分は他者より何が優れていて、何が劣っているのかという観点を感じるきっかけを、開拓していく必要があると思います。それは人から教えても意味がなく、自分自身で作り上げていくことが大事なんです。新しいことに挑戦したいクリエイターに「いいね」と声をかけることで背中を後押しし、その上でクリエイター同士が交流し切磋琢磨することで感性の向上を促進していくことは、いしのまき MANGA lab. ヒトコマであれば実現できる環境にあるでしょう。そのような環境を整えていく上で重要になることは何でしょうか。

丸山:やはり持続することですね。私は60年近くアニメーション制作に関わっているのですが、長期間活動しているとどこかのタイミングで作品が評価されたり、人が集まってくれたりすることがあります。
作品制作もまちづくりも、やり始めたからにはやり続けるべきだと思いますね。いろんなことをやってみた上で、別のこともやることを悪いとは思いません。 ただし、誰がどのように見て評価するかはわからないです。出来栄えではなく、やることに意味があるという気持ちで取り組むことが必要だと思います。
片渕:プロになるのであれば、早期に映画鑑賞の教育をやるべきだと思います。作品に対する良し悪しなどの評価は、自分で撮影をしたあとに良かった点や悪かった点を振り返った上で分かることが、思考のベースとなって行えるようになると思っています。
そのような経験をして初めて感性は養われていきます。そのため、絵を描くことを目的とするのではなく、人の絵が鑑賞できるようになることや、他者が作ったお話を理解できるようになることを目的に活動していくのがいいのではないかと思っています。
人材育成や創作活動が社会とつながるために「みんなで楽しみ、作品をつくる」
石ノ森萬画館が開設された当初、漫画家などの人材を育成することを視野に入れた活用方法が検討されていましたが、現在では展示作品を楽しむ来館者が訪れることが中心となっています。石巻市で漫画文化を軸としたまちづくりを進めていくにあたって、クリエイターの人材育成をすることがあらためて重要であると考えられる際に、地域社会やまちづくりを行う担い手にはどのようなスタンスが求められるのでしょうか。
丸山:石巻市は萬画の国という表現をしていますが、私にはバラバラに見えるので総合体として何かできないかと考えています。石巻市には石ノ森萬画館があるので、漫画を手立てに商売や人集めをすることがダメだとは考えていないんですが、私としては人を育てるグループのような位置付けにするのがいいのではないかと思っています。
片渕: 例えばみんなで一つのテーマを設定して絵を描いていくなかで、自分が綺麗だと思う色を探したり、その色を塗ったりできるような取り組みをすることも大事だと思います。 自分の中で綺麗な色が理解できたり、その色を塗れるようになると美大に進学する人も出てくるかもしれません。 そのような感性を持つ人を育てないと、産業と連携することが技術的な話になってしまうのですが、漫画やアニメーションにおいて重要なことは技術だけではありません。
技術は感性を持っている人に対してついてきます。なので、アニメーションにおいて感性のある動きがわからない人に絵を描かせても結果はついてこないんです。最初から絵が描けるのかどうかが重要なのではなく、 漫画の場合は作品の色はどのように綺麗で、どのように話が面白いのか。 アニメーションの場合は動きを理解できるか、動きに感性があるかどうか理解することが重要であると考えています。


丸山:なおさら人材育成が重要になりますね。ただ、人材育成とものを作るというのはすごく難しいんです。ちゃんとしたものを作るにはプロが作った方が早いですからね。
ただ、街中で漫画やアニメーションの制作経験がない人が作品を作ったとき、プロのレベルまでは及ばなくとも、「街中で作った作品だからこそ素敵だね」と評価される作品であれば作れるのではないかと思います。ヒトコマにおいてクリエイターを育成するつもりがないという前提のもと運営すると、利用者のみなさんも緊張することなく作品制作を楽しむことができるでしょうし、その結果、市民の方が見て楽しむことができる作品ができあがるかもしれません。片渕:本気でプロになろうと思ったら、作品作りも楽しくなくなってしまいますからね。
まとめ
今回は石巻市においてマンガ文化を生かした持続的なまちづくりのあり方を考えるにあたり、丸山さんと片渕さんへインタビューを行いました。
今回の話では、石ノ森萬画館やいしのまき MANGA lab. ヒトコマなどの施設を活用することで、クリエイターが切磋琢磨しながら作品制作を行ない、感性を磨くことを地域全体で行なっていくことが重要であるという視点が提示されたのではないでしょうか。
石ノ森先生は生前、漫画はあらゆる事象を表現できることから「萬画」という表現を用いていました。街全体で未来のクリエイターを育成することはもちろん、その先も既存の枠に囚われず自由な発想で取り組みを進めていくことが「萬画的発想」として、今後のまちづくりのあり方に求められていくことになるでしょう。